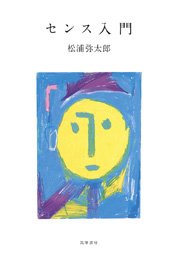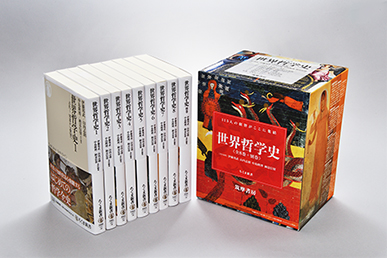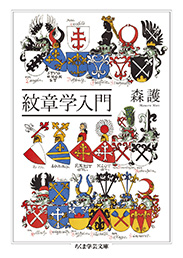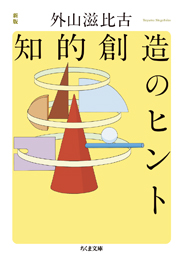ちくま学芸文庫


詩の構造についての覚え書
─ぼくの《詩作品入門》
入沢康夫
著
loading...
1,320
円978-4-480-08655-6
0170
-7-1
2001/08/08
文庫判
304
頁ピンホールを通して外界の風景を捉える装置、「写真鏡(カメラ・オブスキュラ)」。カメラの前身になったといわれるこの機器を通すと、人間の視覚が捉える映像を、客観的に写しとることができる。ダ・ヴィンチやフェルメールなど西洋の画家たちはこの写真鏡を用いて下絵をトレースし、日本では洋風画の先駆者らが取り入れた。カメラマンでもある著者が、人間の目に映った映像がどのように絵画作品になっていったのか、写真鏡をとおして東西美術史を検討しなおす。
序章 「映像」とは
第1章 「写真鏡」とは何か―西欧の写真鏡の通史
第2章 「写真鏡」の渡来
第3章 遠近法による視覚の変革―洋風画の胎動
第4章 遠近法の浸透―蘭学の隆盛と洋風画・銅版画の成立
第5章 日常化した遠近法―洋風画の消化
第6章 写真の発明―写真鏡から写真機へ
本書をお読みになったご意見・ご感想などをお寄せください。
投稿されたお客様の声は、弊社HP、また新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。