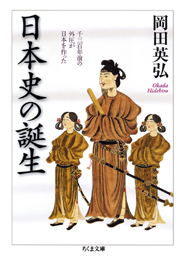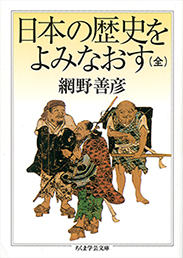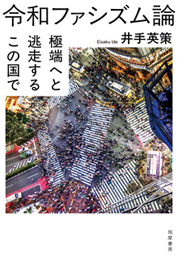新聞
2025/11/23
loading...
小説はいかにしてみずから「小説」であることを騙りうるのか。小説は「小説」と銘打たれているから小説なのではない。小説もまたみずから「小説」であろうと精一杯に努め、これをよそおうがゆえに、はじめて「小説」として認知される。小説が小説たろうとするための"よそおい"や"みぶり"を「表現機構」と名付け、分析概念の核に据えて考察することで、近代小説の全体像に新たな見取り図を示す。第Ⅰ部で、視点、人称、言文一致体、写実主義・個人主義などの理念、自然という概念、私小説、文壇など、複眼的な観点から論じ、第Ⅱ部では個々の作品からその有用性を確認する。文学研究のあり方を実践的に問う名著。 解説 佐藤秀明
はじめに―「表現機構」とは何か
第Ⅰ部
第一章 「小説家」という機構
第二章 「言文一致」のよそおい
第三章 一人称の近代
第四章 「個人主義」という幻想
第五章 反照装置としての「自然」
第六章 表現機構としての「文壇」
第七章 「私小説」とは何か
第八章 自意識と「死」の形象
第九章 交差する「自己」
第Ⅱ部
第一章 森?外『舞姫』―〝重霧の間?にあるもの
第二章 泉鏡花『高野聖』―三つの一人称
第三章 田山花袋『蒲団』―共犯する語り
第四章 森?外『雁』―ロマンの生成
第五章 志賀直哉『和解』―〈不愉快〉と〈調和〉
第六章 有島武郎『カインの末裔』―「自然」と「社会」
第七章 芥川龍之介『舞踏会』―まなざしの交錯
第八章 牧野信一『鱗雲』―夢の自律するとき
第九章 井伏鱒二の初期一人称小説―〈アンコンシアスネス〉であるということ
第十章 小林秀雄『新人Xへ』―「小説」の論理と「批評」の論理
第十一章 太宰治『人間失格』―関係への希求
第十二章 埴谷雄高『死霊』―〈自同律の不快〉
第十三章 戦後文学における〈恥〉の形象―自意識と関係性
あとがき
ちくま学芸文庫版の刊行に当たって
解説(佐藤秀明)
初出一覧
引用本文について
索引
本書をお読みになったご意見・ご感想などをお寄せください。
投稿されたお客様の声は、弊社HP、また新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。