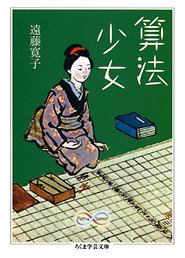あ行
本をさがす
アラン・ムアヘッド(ムアヘッド,アラン)
向井和美(ムカイ・カズミ)
向井 和美(むかい・かずみ):翻訳者。早稲田大学第一文学部卒。訳書に『哲学の女王たち』(晶文社)、『プリズン・ブック・クラブ』『アウシュヴィッツの歯科医』(紀伊國屋書店)など。また、学校図書館司書として生徒たちの読書会を助け、自らも30 年以上にわたり読書会に参加し続けた経験を『読書会という幸福』(岩波新書)で発表している。
向井敏(ムカイ・サトシ)
1930-2002 大阪出身。大阪大学卒。在学中、開高健、谷沢永一らの同人誌「えんぴつ」に参加。電通を経てCM批評『虹をつくる男たち』でサントリー学芸賞受賞。書評家として、広汎な読書に裏打ちされた独自のコラム批評を確立した。
向井承子(ムカイ・ショウコ)
向井雅明(ムカイ・マサアキ)
椋田直子(ムクダ・ナオコ)
東京大学文学部大学院修士課程修了。翻訳家。訳書に『パックス・ブリタニカ 上・下』など多数。
向田和子(ムコウダ・カズコ)
1938年東京生まれ。向田邦子の末妹。邦子が考案した小料理屋「ままや」の経営者。著書に『向田邦子の遺言』『向田邦子の恋文』などがある。
向田邦子(ムコウダ・クニコ)
1929年生まれ。脚本家、エッセイスト、小説家。雑誌記者を経て脚本家となり、「寺内貫太郎一家」「阿修羅のごとく」などテレビ史上に残る数々の名作ドラマを執筆する。小説家として1980年に直木賞受賞。1981年、飛行機事故で急逝。
虫明亜呂無(ムシアケ・アロム)
虫明亜呂無(ムシアケアロム)
虫明亜呂無1923年、東京生まれ。早稲田大学文学部仏文科卒。同大文学部副手を経て、『映画評論』編集部に籍を置き、そののち、文芸批評、映画評論、スポーツ評論、競馬エッセイなど多彩な分野で旺盛な執筆活動を行う。91年に逝去。著書に『肉体への憎しみ』『時さえ忘れて』『野を駈ける光』(ちくま文庫)、『女の足指と電話機』(中公文庫)、『仮面の女と愛の輪廻』(清流出版)などがある。
武者小路穣(ムシャコウジ・ミノル)
1921―2010年。元和光大学教授。専門は日本文化史。著書に『平家物語と琵琶法師』(淡路書房新社)、『襖』、『地方仏1・2』(法政大学出版局)など。
武者小路実篤(ムシャノコウジ・サネアツ)
武者小路辰子(ムシャノコウジ・タツコ)
水野葉舟(ムズノ・ヨウシュウ)
牟田口義郎(ムタグチ・ヨシロウ)
武藤秀太郎(ムトウ・シュウタロウ)
1974年生まれ。専門は社会思想史。早稲田大学政治経済学部卒業。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。学術博士。現在、新潟大学経済学部准教授。著書に『近代日本の社会科学と東アジア』(藤原書店)、編著に『福田徳三著作集』第15・16巻(信山社)などがある。
武藤徹一郎(ムトウ・テツイチロウ)
武藤徹(ムトウ・トオル)
武藤浩子(ムトウ・ヒロコ)
武藤 浩子(むとう・ひろこ):早稲田大学大学院教育学研究科博士後期課程修了。博士(教育学)。IT企業で長年勤務したのちに大学院に進学。東京大学高大接続研究開発センター特任助教等を経て、現在、早稲田大学大学総合研究センター次席研究員(研究院講師)。大学教育学会・奨励賞受賞(2021年度)。著書に『企業が求める〈主体性〉とは何か――教育と労働をつなぐ〈主体性〉言説の分析』(東信堂、2023年)、共著に『〈学ぶ学生〉の実像――大学教育の条件は何か』(勁草書房、2024年)などがある。
武藤浩史(ムトウ・ヒロシ)
武藤 浩史(むとう・ひろし):1958年東京生まれ。英国ウォリック大学大学院博士課程修了。慶應義塾大学名誉教授。専門は英文学。