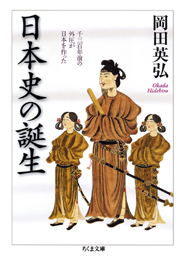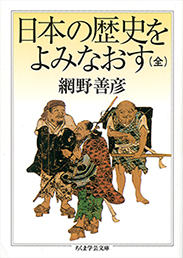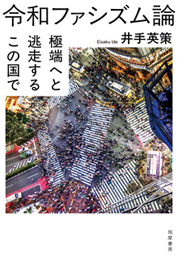富田武
( とみた・たけし )1945年福島県生まれ。成蹊大学名誉教授。専門はロシア・ソ連政治史、日ソ関係史。東京大学法学部卒業、同大学院社会学研究科博士課程満期退学。予備校講師、大学非常勤講師などを経て成蹊大学法学部教授、同法学部長などを務める。著書『歴史としての東大闘争――ぼくたちが闘ったわけ』(ちくま新書、2019年)、『スターリニズムの統治構造――1930年代ソ連の政策決定と国民統合』(岩波書店、1996年)、『戦間期の日ソ関係――1917-1937』(岩波書店、2010年)、『シベリア抑留』(中公新書、2016年、アジア太平洋賞特別賞受賞)など。