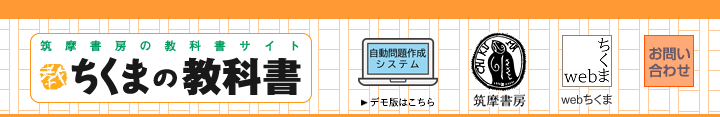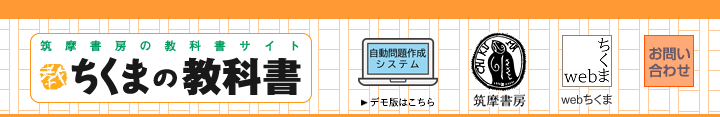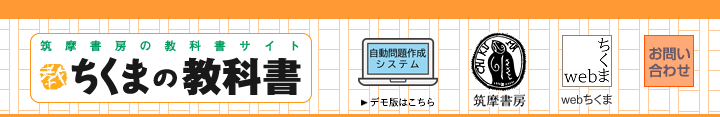 |
|
|
|
|
|
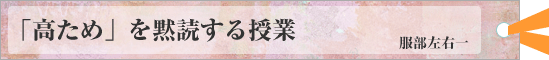
|
|
|
|
|
|
|
|
第1回 私のアンソロジー |
|
|
|
|
|
|
|
1 音読ができない
国語の授業では新しい単元に入るとまずその文章を音読する習慣がある。教師にせよ生徒にせよ、だれか一人が教科書の文章を音読し、教室にいるほかの生徒がそれを静かに聞くというのが授業における導入の一般的な形態になっている。
教師用指導書のどの単元を見ても第一時間目の授業の中に音読が取り入れられている。教師の間で範読とか指名読みとか名付けられたこの音読は授業を行なっていくうえでなくてはならない手続きであり、半ば儀式化されているともいえそうだ。
最近、音読が困難になった。というより、できなくなったと言った方が現状に近いだろう。漢字が読めなくなったとよくいわれるが、ひらがなも読めなくなっている。文あるいは語句としてではなく、一文字一文字を逐語読みする子が増えているからだ。自信がないからぼそぼそ小声でつぶやくように読む。教師にも聞こえない。ましてや教室全体に聞こえるはずがない。せいぜいとなりの生徒に聞こえるくらいだ。
そして、周りは私語の渦である。声が小さいから聞こえない。聞こえないからしゃっべている。うるさいから読むことに集中しない。この悪循環は今に始まったことではないが、これまでは根気よく注意を促すことで何とか静かに聞く時間を作っていたが、注意する時間ばかり長く、授業のエネルギーのほとんどがそれに吸い取られるようになった。 |
|
|
|
|
|
|
|
|