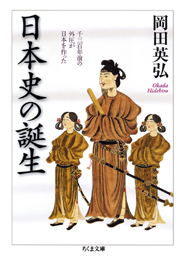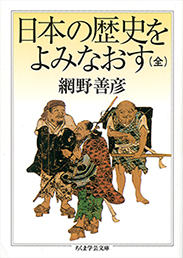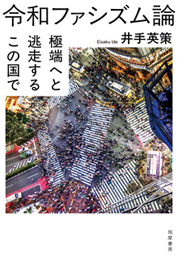茨木のり子
( いばらぎ・のりこ )(1926~2006)大阪に生まれる。詩人。1953年、詩学研究会に投稿していた川崎洋と詩誌「櫂」を創刊。詩集に『見えない配達夫』『鎮魂歌』『自分の感受性くらい』『寸志』『倚りかからず』、エッセイ集に『詩のこころを読む』『一本の茎の上に』などがある。
loading...
タイプの全く違う詩人4人、しかしいずれ劣らぬ世渡りべた、貧乏、もうれつな反逆者―存分に理知と情熱を生きた晶子、忠君愛国に眩惑された自分の罪を負って戦後を生きた光太郎、ルンペン詩人と呼ばれながら気高い精神を詩に賭けた貘、アジア・パリを放浪し、プロレタリア詩にも戦争詩にも組みせず、自分自身の思考力を大切にした光晴。詩にとって時代とは、国家とは。詩人にとって家族とは。詩人の筆によって描破された鮮烈な詩人像。
■与謝野晶子
堺そだちのむすめ
恋のうた
みだれ髪
君死にたもうことなかれ
妻として、母として
黄金の釘
■高村光太郎
高村光雲のむすこ
パリでの人間開眼
父との対立
『智恵子抄』の背景
日本人の「典型」
■山之口貘
ルンペン詩人
求婚の広告
貘さんの詩のつくりかた
ミミコの詩
沖縄へ帰る
精神の貴族
■金子光晴
風がわりな少年
中退の青春
山師のころ
第一回の外遊
詩集『こがね虫』
海外放浪の長い旅
むすこの徴兵をこばむ
戦後になって
文庫版あとがき
本書をお読みになったご意見・ご感想などをお寄せください。
投稿されたお客様の声は、弊社HP、また新聞・雑誌広告などに掲載させていただくことがございます。